「Beats Flex ー fragment designスペシャルエディション」 Apple公式サイトで販売開始
11/03/2022
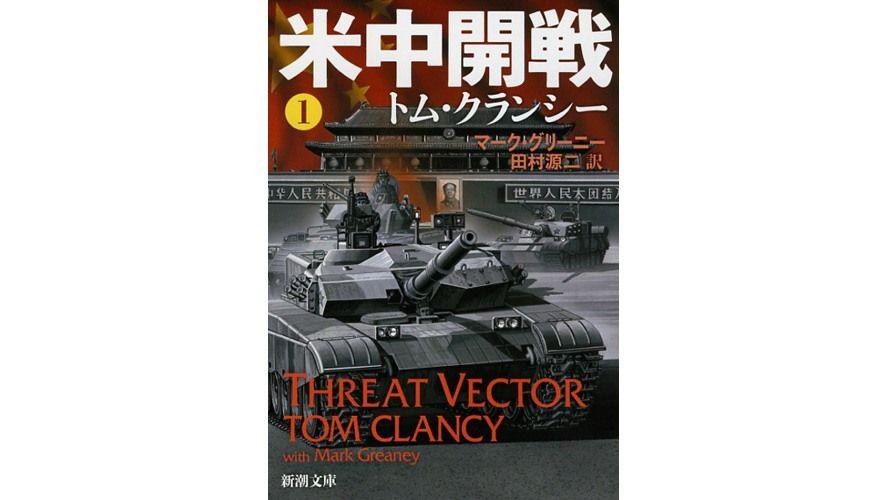
原著が刊行されたのは2012年12月である。 当時の米大統領は、バラク・オバマであり、中国の指導者は、この年の11月の共産党大会において、胡錦濤から習近平に交代した。
しかし、本書に描かれる米中対立の構造は、抜き差しならぬほど深刻化している現在の情勢を先取りしている。習近平率いる中国は、南シナ海の島嶼への領土的野心を露わにし、実効支配を着々と進めているからだ。 読者にとって、この物語でシュミレーションされる米中の軍事衝突は、それだけ興味深いものであるだろう。 インテリジェンスと軍事テクノロジーに精通したトム・クランシーは、どう描いているか。
それはサイバー攻撃から始まった。
手始めは、ネヴァダ州ラスヴェガスにある空軍基地がターゲットだった。ここは無人機(ドローン)を運営する航空団の本拠地であり、その任務は、〈・・・パイロットとセンサー員が遠隔の地にある無人機を飛び立たせ、アフガニスタンやパキスタンやアフリカの侵入を拒む地域の上空を飛びまわらせている・・・〉
パイロットは実際に現地を飛ぶわけではないが、〈最先端のコンピューター、カメラ、衛星コントロール・システムのおかげで、キャノピーから外を見られる本物の戦闘機パイロットと同じくらい戦闘としっかりつながっている。〉
いましも、無人機がパキスタンの上空2万フィート付近を飛行していた。同機の翼下には、ヘルファイア・レーザー誘導空対地ミサイル4発と500ポンドのレーザー誘導爆弾2個が装備されている。
無人機が敵を探知すれば、遠隔操作でただちに攻撃が開始される。
6時間の偵察任務で3時間を過ぎたころ、突然、無人機に異変が起こった。ラスヴェガスから操っていたパイロットの制御が不能となり、同機は勝手に針路を変えてアフガニスタンへ向かって行ったのだ。
モニター前の彼らには、なすすべもなかった。あらゆる自動安全制御システムが作動しない。もはや、誰の目にもこれは、ソフトウエアの不具合などではなく、何者かによって無人機操作のシステムがハッキングされていることは明らかだった。
「まさか、兵器の発射なんてできませんよね?」 と、モニターを凝視していた大尉が不安を口にする。 それが現実のものとなった。 僚機で追撃しようにも間に合わない。まもなく無人機はアフガン駐留米軍の前線作戦基地に到達、もてる兵器のすべてを発射した。
その瞬間の悪夢の映像を、当の空軍基地、CIA本部、国防総省の大勢がモニターで目撃していた。 死者は、アメリカ兵8人、アフガン兵41人にのぼった。
ホワイトハウスのシチュエーションルーム(国家安全保障・危機管理室)の会議室に、ジャック・ライアン大統領以下、国防長官、CIA長官、NSA(国家安全保障局)長官、国家情報長官ら、安全保障を担う高官が集まり、事態の打開策を協議していた。
ハッキングした犯人は依然として不明。ハッカーは、いっさい正体が明らかになるような痕跡を残していない。 いずれにせよ、大統領は真相が明らかになるまで、全無人機の使用停止を命じるしかなかった。
しかし、無人機「乗っ取り」による攻撃は、ほんの前触れにすぎなかったのだ。
本作は、トム・クランシーとマーク・グリーニーによる「ジャック・ライアン」シリーズの4作目にあたる。 主人公は米国大統領のジャック・ライアン。彼は正義感と責任感に満ち溢れ、独裁国家やテロリストを相手に、母国と同盟国を守るためには妥協を許さず、断固として強硬姿勢を貫くタフガイとして描かれる。
このシリーズで、もうひとりの主人公とでもいうべき登場人物が、大統領の長男であるジャック・ジュニアである。彼は民間の極秘情報組織「ザ・キャンバス」の情報分析官兼工作員として活躍する。「ザ・キャンバス」は、ライアンの発案で創設された。表向きは金融投資会社の看板を掲げているが、有能な現地工作員とIT専門家を擁し、国家情報長官の極秘の指示により、公の政府機関では動くことのできない事案に対処する。
現地工作員は少数精鋭の5人で構成される。彼らは米軍特殊部隊や情報機関から選抜されており、射撃、武術に優れ、最前線での戦闘も辞さない猛者の集まりだ。 一連のシリーズでは、その都度、彼らの個性が魅力的に描き分けられており、迫真の戦闘シーンも作品の人気を呼ぶ要素になっている。
本作では、ホワイトハウスの動きと並走するように、「ザ・キャンパス」のメンバーが香港、北京を舞台に、縦横無尽に活躍する。本シリーズのファンにとっては、それこそが醍醐味であろう。今回も読者の期待を上回る、抜群の面白さがある。
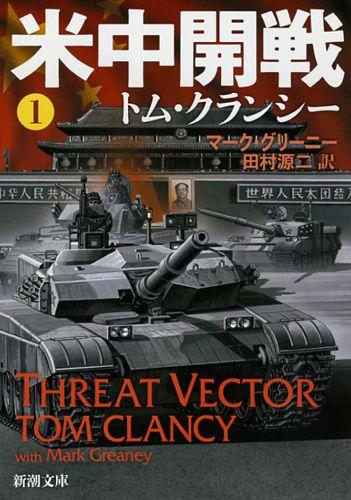
物語で描かれる中国の現状はこうだ。 米国と対立を深める中国の指導層は、葦真林(ウェイ・ヂェンリン)国家主席兼中国共産党中央委員会総書記と、蘇克強(スー・コーチアン)軍事委員会主席の二頭体制になっている。
葦は経済専門のテクノクラートであり、蘇は生粋の軍人あがりで今や人民解放軍を牛耳る実力者。両人とも父親が中国共産党の大幹部で、彼らは「太子党」と呼ばれる2世グループの一員として、ともにそれぞれの道でエリートコースを歩んできた。
ここまでの中国は、葦総書記の進めてきた経済特区政策のおかげで、毎年2桁の経済成長を遂げてきた。 しかし、成長の勢いにも陰りがみられるようになる。加えて貧富の格差が拡大し、民主化を求める反政府運動も顕在化しつつあった。 これまで人民解放軍や武装警察による弾圧で、反乱分子を根絶やしにしてきたが、経済の停滞で共産党常務委員会の他の幹部からも、総書記に批判の声が上がるようになる。 あわや失脚の危機にあった葦を救ったのが、蘇だ。彼は人民解放軍の武力を背景に、党幹部の不満を抑え込んだのである。
葦と蘇は、さらなる中国の発展をもとめ、強硬な外交政策を推し進めていく。 第一段階は、フィリピン、インドネシア、インドとの間で紛争になっている南シナ海の領有権問題にケリをつけること。 第二段階は、香港の本土への完全な組み込みで、深圳の経済特区に吸収してしまう。 第三段階が、台湾の併合である。
葦は、それを5年以内に実現させるとするが、蘇は人民解放軍の武力を用いて一気呵成に、1年以内で決着をつけると目論んでいる。 むろん、中国が南シナ海に進出すれば、当然、アメリカが圧力をかけてくることが予想される。横須賀を母港とする空母「ロナルド・レーガン」の打撃群が東シナ海でにらみをきかせ、いつでも南シナ海へ進出できるよう有事に備えているからだ。 中国はどうやってアメリカの反撃を抑え込むつもりなのか。現実の状況を踏まえて、ここはおおいに関心のもたれるところである。
彼らは、ついに開戦を決意する。その場面。
「同志、われわれはライアンに中国がやっていると気取られないようにして先制攻撃を仕掛ける。われわれなら、攻撃者が中国だとわからないようにして攻撃できる」と、対米強硬派の蘇は主張する。 「そんなにうまくいくのだろうか?」
葦は半信半疑だが、蘇はこう言って押し切るのだ。「攻撃のための基盤はできあがり、準備万端ととのっている。まだわれわれが優位にあるうちにそれを有効に利用しないといけない。ぜひともそうする必要がある。いまならわれわれの戦闘能力は絶大だ」
中国共産党は、毎年20%を超える勢いで国防費に国家予算をつぎ込んできた。 蘇の見るところ、陸海空の通常戦力では米軍と互角か、それ以下。しかし、相手をはるかに凌駕するサイバー攻撃の能力を保持している。彼は、人民解放軍の傘下に、ひそかにハッカー集団を育成し、それがいまでは世界最強のサイバー軍団になっていたのである。
本稿の冒頭で紹介したように、密かに、戦端は開かれた。まず、サイバー攻撃で無人機の戦力を無力化することに成功する。 間髪を置かず、人民解放軍が南シナ海の島嶼に上陸を開始した。中国海軍は、フィリピン、インドの艦船を攻撃する。あわせて空軍の戦闘機が台湾の領空を侵犯。台湾機がスクランブル発進し、さらに空母ロナルド・レーガンから米軍機も飛び立った。米中はついに戦闘状態に入った――。
これに続く戦闘シーンや人民解放軍の武力侵攻のあり様など、そこはトム・クランシーならではのリアリティと緻密さ、迫真性がある。 この先、どう米中両国の衝突が紛争へと拡大していくか、ここから先の展開が、本作の最大の読みどころである。
あと少しだけ戦況を紹介しておきたい。「新しい戦争のかたち」とは、まさにこうなのだろう。アメリカに未曾有の危機が訪れる。
ライアン大統領は、戦争を回避しようとするものの、中国の攻勢に押しまくられる。 蘇は、人民解放軍の侵攻とあわせて、さらに大がかりなサイバー攻撃を仕掛けてきた。 国防総省のネットワークに侵入し、サーヴァーをダウンさせた。これにより全米軍のコンピューター・システム間の連絡能力の大半が失われた。
さらに民間のインフラにも攻撃が加えられる。航空機を管制する連邦航空局のネットワークや、東海岸のメトロのシステムがダウン、一般の携帯電話も通じなくなる。当然、米国民はパニック状態。 極めつけは、米国南部アーカンソー州にある原子力発電所のシステムに入り込み、冷却用軽水ポンプを停止させたことだ。原子炉が制御不能に陥り、炉心温度が急激に上昇、あわや炉心溶融(メルトダウン)寸前という事態にまで追い込まれる。
米国のコンピューター・システムは、なぜ、これほどまでに脆弱なのか。 このあたり、ライアン大統領と、米軍のサイバー軍司令官との会話が興味深い。 ライアンは尋ねる。「いったいなぜ、われわれはサイバーセキュリティという分野で中国にこれほど遅れをとってしまったのかね?」
司令官の答えはこうだ。「・・・要するに、中国には非常に頭のいい者が何百人もいるということ、それに尽きます。しかも、その多くはここアメリカで学んだ者たちです。そういう者たちが祖国に帰って、われわれに対して武器をとって戦うのと本質的には変わらない現代的な戦いをしているのです」
サイバー戦に必要とされる優秀なハッカーは、ロシアか中国、インドで生まれた20代の若者である。アメリカで学んでも、外国籍の彼らは、米国政府の最高機密に触れる職業に就くことができない。 サイバー軍司令官は、何年も前にサイバー攻撃に関する報告書を提出していたが、一顧だにされなかったと嘆く。「アメリカという国は、まだ起こっていないことに備えるのが苦手なのです。わが国では、サイバー戦は漠然とした概念、ファンタジーでしかなかったのです・・・・・・今朝までは」
いよいよ反撃は手詰まりとなったか。ライアンの問いかけに、国防省の海軍作戦立案部門のトップになる海軍提督が答える。
「・・・わが海軍艦船が用いうる防衛手段はたくさんあります。しかし、そうした防衛手段の多くは堅固な通信ネットワークと衛星の良質なデータに頼っており、いまはそのどちらも乏しいという状態です」
近代兵器の盲点とはかくや、というわけである。
事態を打開するためには、サイバー攻撃の拠点となっている施設をピンポイントで破壊するしかない。しかし、それはいったいどこにある?
その疑問に答えられる者はいない。 中国は、開戦に至るまでに、CIAのイントラネット(組織内のプライベートネットワーク)の侵入に密かに成功しており、北京在住の米大使館員に偽装した工作員やNOC(公式偽装で護られていない非合法工作員)を割り出し、次々と国外追放していた。アメリカの情報収集活動は手薄となり、もはや現地で頼りになる要員はいない。
鍵を握るのは、「ザ・キャンパス」の極秘任務だった。 彼らは、別のサイバー犯罪を追いかけるうち、中国のハッカー集団の存在に行き当たる。 はたして、ライアン大統領は、どうやって中国の野望を阻止するのか。 本作は、近未来の戦争のありかたに警告を発した書でもある。
そして、現実のサイバー・テクノロジーは、本作の発表時から、さらに高度化されている。日本が米中戦争に巻き込まれたらと考えると、戦慄せざるをえない。
トム・クランシー、マーク・グリーニー(共著)、田村源二(翻訳)発行:新潮社文庫版:第1巻321ページ、第2巻328ページ、第3巻311ページ、第4巻335ページ価格:各巻とも630円(税抜き)発行日:第1、2巻2014年1月1日、第3、4巻同年2月1日ISBN:第1巻978-4-10-247253-8、第2巻978-4-10-247254-5、第3巻978-4-10-247255-2、第4巻978-4-10-247256-9